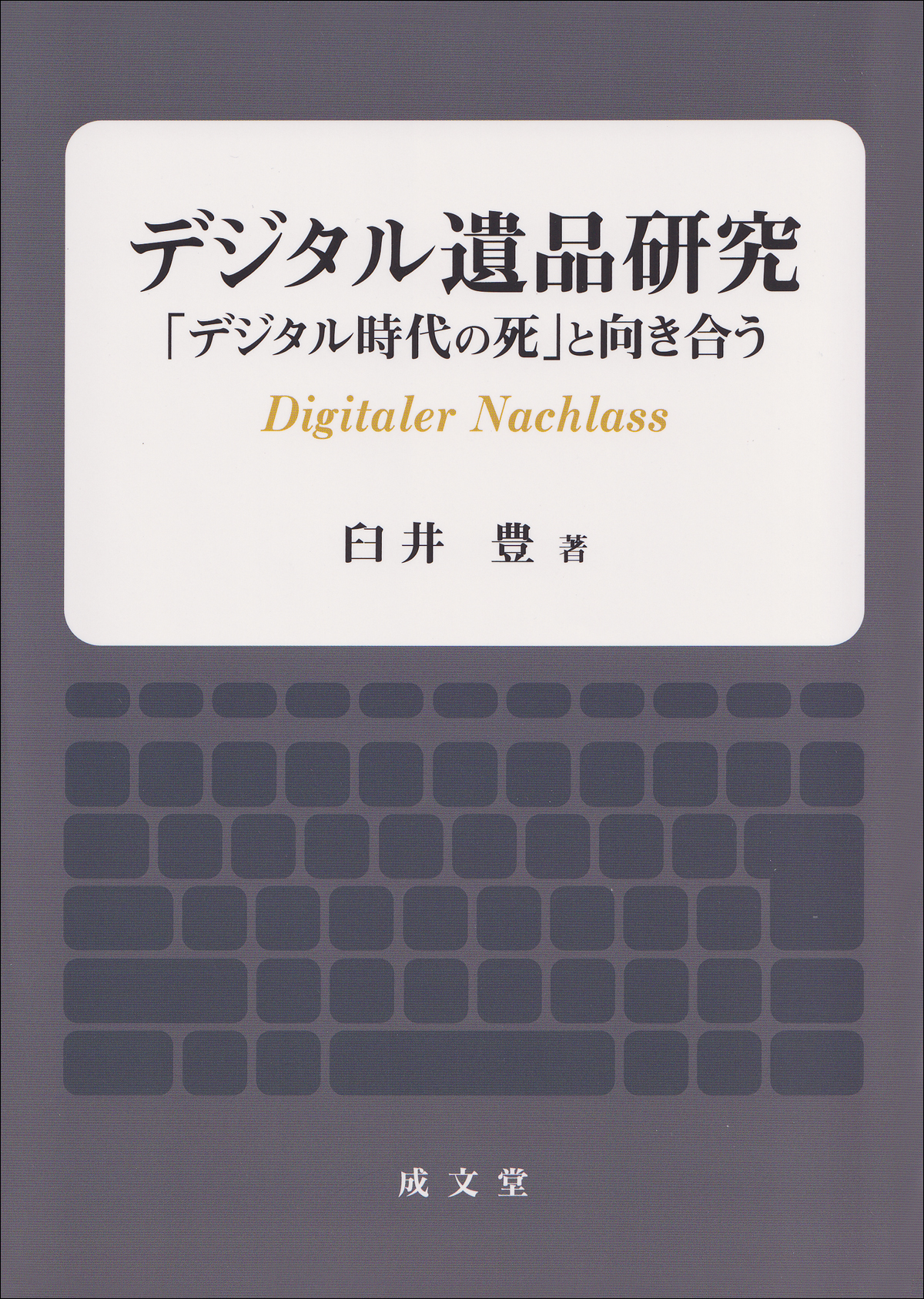
デジタル遺品研究
「デジタル時代の死」と向き合う臼井 豊 著
定価:11,000円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2025年09月20日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
542 -
ISBN:
978-4-7923-2821-4
書籍購入は弊社「早稲田正門店インターネット書店」サイトでの購入となります。
《目 次》
はじめに―「はしがき」も兼ねて― 1
1.デジタル時代の「デジタル遺品」という現代的法律問題 1
2.「デジタル遺品」研究を始める契機となった素朴な疑問 4
3.本書のスタンス 7
4.本書・各章の概要 13
第1章 デジタル遺品の死後承継という現代的問題の出現―ドイツ初のLG Berlin 2015年12月17日判決を中心に―(2016年研究) 29
第1節 はじめに 29
(1) 「デジタル遺品」という現代的問題(29)
(2) 「デジタル遺品」の法的運命をめぐる議論の盛り上がり(30)
(3) 本章の考察対象と順序(33)
第2節 LG Berlin 2015年12月17日判決33
(1) 判決要旨(33)
(2) 事実概要(34)
(3) 判決理由(35)
第3節 LG Berlin 2015年12月17日判決の解説・分析 41
(1) デジタル遺品の相続性・包括承継の原則的承認と法的理由づけ(42)
(2) 例外的な相続性排除の可能性?(45)
(3) 特別法上の守秘規定との比較?(47)
(4) 利用規約に関わる問題(47)
(5) 死後人格権を理由としたアクセスの不許可?(48)
(6) 通信の秘密によるアクセスの不許可?(50)
(7) データ保護法(BDSG)違反の可能性?(52)
(8) 相続人の情報請求権の承認(52)
(9) 著作権法上の検討に立ち入る必要のなかった理由(53)
(10) その他雑感(53)
第4節 おわりに 56
(1) デジタル遺品をめぐる紛争の予防策について(56)
(2) デジタル遺品の相続財産性について(58)
(3) 「利用契約」の性質決定と当事者の意思探求・解釈(58)
(4) 現代のデジタル社会における民法のアップデートの必要性?(60)
第2章 デジタル遺品訴訟のゆくえ―BGH 2018年7月12日判決とその解説・論評―(2019年研究) 83
第1節 はじめに 83
(1) 「デジタル遺品」問題と初訴訟のゆくえ(83)
(2) 本章の考察対象・順序(85)
第2節 デジタル遺品訴訟の経過 85
(1) 事実概要(85)
(2) 第1審:LG Berlin 2015年12月17日判決(86)
(3) 第2審:KG 2017年5月31日判決(86)
第3節 BGH 2018年7月12日判決 88
(1) 判決要旨(88)
(2) 判決理由(88)
第4節 BGH 2018年7月12日判決の解説・分析 113
1.SNS利用契約関係の相続性の明確な承認 113
(1) 「利用規約によるアクセス請求権の相続性排除」の否認(114)
(2) 「追悼規律の契約内容化」の否認と約款規制への抵触可能性(114)
(3) 契約当事者の義務の非一身専属性(115)
(4) 通信相手の信頼の要保護性の欠如(116)
(5) 「特定の人」ではなく単なる「アカウント」への伝達・提供義務(116)
(6) 保存データの財産権的内容を基準にアクセス権の相続性を区別する見解の不採用(117)
2.死後人格権、通信の秘密およびデータ保護法(GDPR)による相続性の非排除118
(1) 死後人格権による相続性の非排除(118)
(2) 通信の秘密による相続性の非排除:「相続人≠他人(TKG 88条3項)」という解釈の導出(118)
(3) データ保護法(GDPR)による相続性の非排除(119)
3.その他 123
第5節 リツェンブルガーによるBGH判決の評価と影響 123
1.全「デジタル財産」の相続性 124
(1) BGH判決に対する好意的評価(124)
(2) BGH判決の射程(127)
2.通信の秘密を侵害しないこと 128
3.GDPRに違反しないこと 130
4.相続証明 130
5.展望 131
第6節 おわりに―次章以降の研究方針― 132
(1) BGH判決と第1審LG判決との比較分析・検討(133)
(2) 素朴な疑問に関わって(133)
(3) 第2審KG判決の分析・検討の必要性(142)
(4) 「現代的なデジタル遺品」問題にふさわしい解決を求めて(143)
(5) 本件特殊事情・ニーズへの暫定的対応(144)
(6) 本件から離れて......(145)
付録 Facebook-BGH判決以後の新たな事件の登場―「クラウド・サービスに関わるデジタル遺品」について― 151
第3章 デジタル遺品の登場により法律はアップデートを必要とするか―Facebook-BGH 2018年判決前後におけるルディガの見通し・評価を中心に―(2020年研究) 185
第1節 はじめに 185
(1) 現代におけるデジタル環境の浸透とプライバシーの存在感(185)
(2) 本章の考察対象と順序(187)
第2節 「デジタル遺品」問題と関心を高めた諸要因189
1.「デジタル遺品」という現代的法律問題 189
2.「デジタル遺品」への問題関心を高めた技術的・社会的・経済的要因 194
第3節 現代社会のデジタル化に伴う民法典のアップデート問題 195
(1) 現代社会のデジタル化への法的対応という問題意識(195)
(2) 相続法を待ち受ける「デジタル遺品」・「デジタル遺言」問題とアップデート(198)
(3) デジタル・アップデートへの及び腰?(200)
(4) わが国におけるデジタル問題への関心・対応(201)
第4節 「デジタル遺品」に関する新たな特別規律の必要性に対するルディガの見通し 202
1.前提概念と問題状況 202
(1) 前提となる「デジタル遺品」概念について(202)
(2) 「デジタル遺品へのアクセス」問題(204)
2.Facebook事件につき対峙する第1審LG判決と第2審KG判決について 204
(1) 「相続権の保障」か「通信の秘密の保護」か(204)
(2) デジタル遺品の相続性を排除する約款と内容規制への抵触(205)
3.デジタル遺品を構成する「電子メール」の相続性について 206
(1) 電子メールが被相続人の記憶媒体に保存されているか否かによる場合分け(206)
(2) 電子メールの財産的価値の有無による内容峻別的手法の否認(209)
(3) 電子メール・アカウント自体について(210)
4.データ保護法(BDSG・GDPR)との関係 211
5.死後人格権との関係 212
6.通信の秘密に関するGG 10条と、その具体化法としてのTKG 88条 213
7.総括 215
第5節 BGH判決に対するルディガの評価 216
(1) 「SNS利用契約関係の相続性」の承認と、「相続性を排除した約款の有効性・内容規制」問題(217)
(2) 「通信相手の人格権」の非妨害と「通信内容による相続性峻別」の否認(219)
(3) 「通信の秘密」の非妨害と「TKG 88条の追加修正」不要(220)
(4) 「柔軟性を備えた相続法」の改正不要論(221)
第6節 おわりに 221
1.筆者の基本姿勢・方向性の確認 221
(1) デジタル・プライバシーによる相続権の制約?(221)
(2) デジタル化社会のBGBアップデート問題(223)
2.BGH判決に関するレスタの比較法研究とヨーロッパ諸国の立法動向 226
3.次章の研究対象:アウマンたちによる憲法上の基本権的アプローチ 229
4.Facebook事件のその後 231
第4章 デジタル遺品の相続性に関する批判的考察―SNSアカウント事例における「死後の人格保護」と「通信の秘密」を中心に―(2021年研究) 279
第1節 はじめに 279
1.「デジタル遺品」初訴訟と「デジタル・プライバシー」の軽視 279
2.本章の目的・順序 283
第2節 前章までの研究成果として判明した論点の再整理 286
第3節 SNSの特性・利用実態から「デジタル・プライバシー」を重視するアウマンたちの批判的見解 289
1.Facebook-BGH判決に対する分析視角 289
(1) 憲法学的アプローチの必要性(289)
(2) データ自体の相続性に関わって(290)
2.相続権を制限しうる「死後の人格保護」 290
(1) 死後の人格保護とその代弁者(291)
(2) 「死後の人格保護」の現代的意義・重要性(292)
(3) アナログ遺品たる「日記」等との比較(294)
3.通信相手の基本権としての「通信の秘密」 297
(1) SNS事業者の基本権拘束とその射程(297)
(2) 「通信の秘密」の保護領域の拡大(299)
(3) 通信の秘密の「侵害」(299)
(4) 「アナログ遺品との同一処理」への疑義(301)
4.アウマンたちの総括 302
第4節 筆者の雑感・補足―アウマンたちの見解の分析・評価 を兼ねて― 303
(1) 憲法学的アプローチについて(303)
(2) データ自体の相続性に関わる「データ所有権」論について(304)
(3) 所有者不明データの企業への帰属について(306)
(4) 死後の人格保護に関わって(306)
(5) 通信の秘密に関わって(310)
(6) 「死者は未成年者であった」というFacebook事件における個別特殊事情(312)
(7) Facebook-BGH判決の事例判断的位置づけと限定的射程(313)
(8) 民法典のデジタル法への脱皮という方向性について(314)
第5節 Facebook事件の終着点―判決内容の執行に関わるBGH 2020年8月27日決定― 315
第6節 おわりに 317
(1) 次章以降の研究について(317)
(2) デジタル遺品問題の集約された原点回帰事例(318)
補節 第2のFacebook事件と「立法」動向 320
(1) 第2のFacebook事件(320)
(2) 「立法」動向―「通信の秘密」を制限するTTDSG 4条の新設―(321)
第5章 「デジタル遺品」研究の原点回帰 ―開拓者ヘーレンを中心に―(2021年研究) 357
第1節 はじめに 357
第2節 ヘーレンの研究論文(2005年)と判例評釈(2018年) 358
1.研究論文「死とインターネット」(2005年) 358
(1) 死者の電子メールへのアクセス権限と限界(358)
(2) 通信の秘密の侵害および処罰可能性(360)
(3) 総括(361)
2.Facebook-BGH判決の評釈(2018年) 362
第3節 ヘーレンによる問題提起・主張のその後 363
(1) 死後の人格保護について(363)
(2) 通信の秘密について(364)
(3) 死者による生前の規律の重要性などについて(366)
(4) 筆者の見方とABGBの「追憶」構想(367)
第4節 おわりに 367
(1) 今後期待される「デジタル遺品」研究(367)
(2) ゲッスルによる新たな規律提案(368)
補節 「デジタル遺品」に関わる当時最新の文献・得られた情報、新サービスなどに対する補足 370
(1) 新たな文献・得られた情報など(370)
(2) わが国におけるデジタル遺品サービス充実への動き(374)
(3) わが国での「デジタル遺品」処理をめぐるトラブル?(374)
第6章 通信の秘密・データ保護の観点からの「デジタル遺品への相続人のアクセス」に関する批判的考察―本家マルティーニの最新動向と新たなTTDSG 4条の規定を中心に―(2022年~2023年研究) 391
第1節 はじめに 391
1.筆者の研究に対する反応等について 391
2.本章の目的と考察対象・順序 394
第2節 マルティーニの最新動向 399
1.通信の秘密と「他人」(旧TKG 88条3項1文) 399
(1) Facebookは電気通信事業者か?(400)
(2) 「他人」としての相続人?(401)
2.個人データの「適法なデータ処理」とされるための要件(GDPR 6条1項)をめぐって―
通信相手の個人データの保護― 403
(1) 契約の履行にとって必要なデータ処理(GDPR 6条1項b号)(404)
(2) 正当な利益の保護(GDPR 6条1項f号)―利益較量(405)
3.「センシティブ・データ」処理の禁止(GDPR 9条1項)408
4.今後成立が予想されるePRおよびGDPRとの関係 410
第3節 デジタル遺品に関わるTTDSG 4条による「通信の秘密」の制限―Facebook-BGH判決の立法・明文化― 411
第4節 おわりに 415
(1) EUのデータ・プライバシー保護関連規律の最新動向(415)
(2) 診療情報に関する「死後の守秘義務」規律への着目(416)
(3) 欧州委員会の提案する「デジタル・ディケイドに向けたデジタルの権利と原則に関する欧州宣言」に関わって(416)
(1) 「デジタル相続」のために通信の秘密を制限したTTDSG 4条に関わって(418)
(2) SNSアカウントの非相続約款条項について(420)
(3) 2022年3月の第16回ドイツ相続法大会・オープニングイベント「デジタル遺品の中の暗号(仮想)通貨」を中心に(420)
(1) 「個人データ」の複合的な性質・価値―人格的性質・価値+α(421)
(2) 「デジタル追憶・追悼」への将来的潮流(422)
補節 〔ヒアリング調査〕京都市個人情報保護条例16条2号に関する「死者の個人情報の非開示」実務について 424
付録 「死者の金融資産」情報へのアクセス 427
おわりに―今後のデジタル遺品研究への橋渡し―(2024年研究) 481
1.相続人による被相続人のSNSアカウントの積極的な継続利用の可能性について 483
2.相続人による被相続人のゲーム・アカウントの積極的な継続利用の可能性について 490
3.相続人による被相続人のアバターの相続・積極的な継続利用の可能性について 496
4.「デジタル遺品」問題を解決するための「デジタル生前配慮」のすすめ 500
5.「デジタル遺品」問題を解決する「デジタル遺言」の解禁・導入へ 503
6.「デジタル遺品」という法律問題を身近なものとして考えていただく契機に...... 506
付録 「相続人による被相続人のSNSアカウントの積極的な継続利用」を争うInstagram事件の新登場―本書脱稿後・校正段階に接した裁判例速報― 508