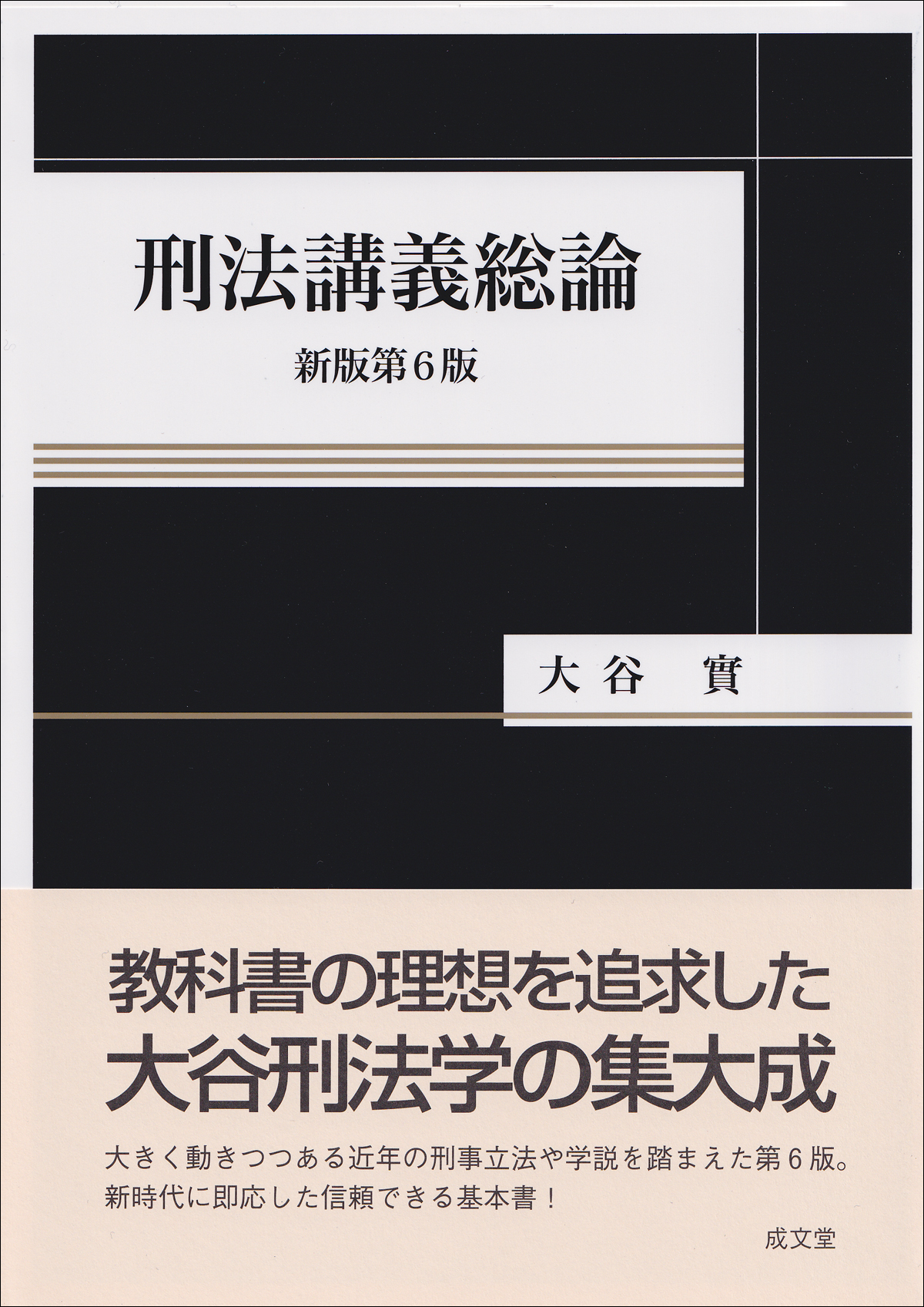
刑法講義総論 新版第6版
大谷 實 著
定価:4,400円(税込)-
在庫:
在庫があります -
発行:
2025年03月01日
-
判型:
A5判上製 -
ページ数:
640 -
ISBN:
978-4-7923-5438-1
《目 次》
はしがき
凡例
第1編 刑法の基礎
第1章 刑法と刑法学... 3
1 刑法の意義... 3
1 刑法の概念 3
*刑法の定義
*法典とは
2 刑法の目的・任務 4
3 刑法の分類 5
4 刑法の規範 6
*法定犯の自然犯化
2 刑法の社会的機能... 7
1 規制機能 7
2 社会秩序維持機能 7
(1) 法益保護機能
(2) 人権保障機能
(3) 謙抑主義
(4) 社会秩序維持と人権保障との関係
3 刑法と社会倫理...10
1 社会倫理と刑法との関係 10
*非犯罪化
2 刑法における社会倫理の機能 11
4 刑法学...13
1 刑法解釈学 13
2 基礎刑法学 13
3 刑事法学 14
第2章 刑法学の歩み...15
第1節 古典学派と近代学派...15
1 古典学派...15
2 啓蒙思想と刑法理論...16
1 ベッカリーア 16
2 フォイエルバッハ 16
*ベンサム
3 啓蒙思想と刑事立法...17
1 フランス 17
2 ドイツ 18
3 イギリス 18
第2節 近代刑法学の展開...19
1 応報刑論...19
1 カントとヘーゲル 19
2 ビンディング 20
2 古典学派と近代学派...21
1 古典学派の特徴 21
2 近代学派(新派) 21
(1) イタリア学派
(2) リスト
(ア) 行為者主義
(イ) 意思決定論
3 学派の争いとその克服...23
1 ビルクマイヤーとリスト 23
2 学派対立の克服 25
4 20世紀の刑事立法...26
1 第二次大戦まで 26
(1) 刑罰と保安処分
(2) 新古典学派
*新社会防衛論
(3) 刑罰一元主義
2 第二次大戦後 28
第3節 わが国における刑法の歩み...28
1 旧刑法まで...28
2 旧刑法・現行刑法...29
1 旧刑法の制定 29
2 現行刑法の制度から終戦まで30
(1) 現行刑法の背景と性格
(2) 学界の状況
(3) 改正刑法仮案
3 第二次世界大戦以降...31
1 立法の動向 31
2 学派の争いの状況 32
3 戦後の刑法改正作業 33
(1) 二つの草案
(2) 改正刑法草案に対する批判
*日弁連の態度と刑法研究会
4 刑事立法の活性化 34
5 今後の学説の動向 36
第3章 刑法理論...38
第1節 犯罪論...38
1 非決定論と決定論...38
2 行為主義と客観主義...39
3 法益保護主義とその修正...40
第2節 刑罰論...40
1 刑罰の理念をめぐる対立...40
*刑罰論の史的展開
2 刑罰の本質...42
1 目的刑主義と応報原理 42
2 統合主義 42
*併合説批判
3 二元主義 43
*分配説
3 刑罰の機能...44
1 報復機能 44
2 一般予防機能 44
*一般予防刑論の再興
3 特別予防機能 45
4 各機能の関係 46
(1) 残虐な刑罰の禁止
(2) 個人の尊重
(3) 三つの機能の統合
4 刑罰の種類...48
1 刑罰の分類 48
2 現行法上の刑罰 48
*行政罰
第4章 刑法の法源と解釈...50
第1節 罪刑法定主義...50
1 意義および沿革...50
1 意義 50
2 沿革 50
(1) 欧米
(ア) マグナカルタから人権宣言へ
(イ) 罪刑法定主義の危機
(ウ) 罪刑法定主義の確立
(2) 日本
*現行刑法典と罪刑法定主義
2 罪刑法定主義の内容...53
1 理論的根拠 53
(1) 三権分立論と心理強制説
(2) 二つの要請
2 法規上の根拠 54
3 派生的原則 55
第2節 刑法の法源...55
1 法律主義...55
1 意義 55
2 政令と罰則 56
*包括的委任 *猿払事件
3 条例と罰則 57
*法律による授権
4 慣習・条理,判例 58
(1) 慣習・条理
(2) 判例
2 刑罰法規適正の原則(実体的デュー・プロセス)...59
1 意義 59
2 明確性の原則 60
*明確性に関する判例
3 過度の広範性の理論 61
*合憲的限定解釈
4 無害な行為の不処罰 63
5 罪刑の均衡 64
6 絶対的不確定刑の禁止 64
第3節 刑法の解釈...65
1 類推解釈の禁止...65
1 類推解釈の意義 65
*類推解釈肯定説
2 刑罰法規の解釈の限界 66
*厳格解釈と判例
*拡張解釈と類推解釈
*裁判員制度と刑法の解釈
2 類推解釈の許容...69
*参考となる判例
第2編 犯罪
第1章 犯罪理論...73
第1節 犯罪の基本概念...73
1 当罰的行為と可罰的行為...73
1 当罰的行為 73
2 可罰的行為 73
2 犯罪成立要件...74
1 意義 74
2 行為 74
3 構成要件該当性 74
4 違法性 75
5 責任 76
*客観的処罰条件
3 犯罪成立阻却事由...76
1 意義 76
2 違法性阻却事由 77
3 責任阻却・減軽事由 77
*人的処罰阻却事由
第2節 犯罪論の体系...77
1 犯罪論体系の意義...77
*体系的思考から問題解決的思考へ
2 犯罪要素の体系化...78
1 四つの要素 78
2 形式性と実質性 79
3 違法性判断と責任判断 80
3 形式的犯罪論と実質的犯罪論...80
1 総説 80
2 構成要件と形式性 81
4 犯罪の種類...82
1 自然犯・刑事犯と法定犯・行政犯 83
2 政治犯と確信犯 83
3 親告罪と非親告罪 83
第3節 行為...84
1 総説...84
2 行為をめぐる諸説...84
1 自然的行為論 84
2 目的的行為論 85
3 人格的行為論 86
4 社会的行為論 87
3 刑法における行為...87
1 意思支配の可能性 87
(1) 自然現象との区別
(2) 忘却犯の行為性
2 外部的態度 89
(1) 社会生活上意味ある態度
(2) 統一機能と限界機能
(3) 行為の定義
*行為性が問題となった事例
第2章 構成要件...91
第1節 構成要件の概念...91
1 構成要件の意義...91
1 意義 91
*構成要件の理論
2 構成要件の内容 93
*定型説
3 構成要件と違法性・責任との関係 94
(1) 学説の検討
(2) 原則と例外
*違法・責任類型説に対する批判
2 構成要件の機能...96
1 理論的機能 96
*刑事訴訟法上の機能
2 社会的機能 97
3 構成要件の種類...98
1 基本的構成要件・修正された構成要件 98
(1) 両者の意義
(2) 両者の関係
*修正された構成要件の例
2 閉ざされた構成要件・開かれた構成要件 99
3 積極的構成要件と消極的構成要件 99
4 消極的構成要件要素の理論 100
第2節 構成要件要素...100
1 構成要件該当性と構成要件要素...100
1 構成要件該当性 100
(1) 該当性の判断
(2) 価値関係的事実判断
(3) 「該当」と「充足」
2 構成要件要素 101
2 客観的構成要件要素...102
1 行為の主体 102
(1) 身分犯
(2) 法人の犯罪能力
(ア) 意義
(イ) 学説の対立
*判例の態度
(ウ) 根拠
(エ) 現行法上の法人処罰
(a) 法人処罰の形式
*犯罪能力否定説と法人処罰
(b) 両罰規定の処罰根拠
(c) 両罰規定の適用
*法人処罰の動向
2 行為の客体 108
3 行為の状況 108
4 行為 109
5 行為と結果 109
(1) 結果犯・挙動犯
(ア) 結果的加重犯
(イ) 挙動犯
(2) 実質犯・形式犯
(3) 実害犯・危険犯
(ア) 抽象的危険犯
(イ) 形式犯との区別
(ウ) 準抽象的危険犯
(エ) 具体的危険犯
(4) 即成犯・状態犯・継続犯
(ア) 即成犯
(イ) 状態犯
(ウ) 継続犯
*犯罪の既遂時期と終了時期
6 行為と結果との因果関係 113
3 主観的構成要件要素...113
1 意義 113
2 一般的主観的要素 114
(1) 構成要件要素としての故意・過失
(2) 故意と過失の関係
*「特別の規定」と判例
(3) 故意・過失の体系的地位
3 特殊的主観的要素 116
(1) 目的犯
(2) 表現犯
*傾向犯
4 構成要件要素の分類...117
1 記述的構成要件要素と規範的構成要件要素 117
(1) 記述的構成要件要素
(2) 規範的構成要件要素
2 違法類型および責任類型としての構成要件要素 118
(1) 違法類型としての要素
(ア) 客観的構成要件要素
(イ) 主観的構成要件要素
(2) 責任類型としての要素
*構成要件的故意・過失
5 構成要件の解釈...120
1 構成要件の確定 120
2 開かれた構成要件の場合 121
3 規範的構成要件要素の場合 121
4 修正された構成要件の場合 122
第3節 構成要件該当性...122
第1款 実行行為の意義...122
1 構成要件該当性の意義...122
2 実行行為...123
1 意義 123
*実行行為の多義性
2 実行行為の態様 125
第2款 不作為犯...126
1 総説...126
1 作為犯と不作為犯 126
*行政取締法規上の真正不作為犯
2 不作為犯の理論 127
(1) 不作為の行為性
(2) 不作為の因果性
(3) 不作為犯と違法性
3 不真正不作為犯の問題性 129
*不真正不作為犯と罪刑法定主義
4 不真正不作為犯の実行行為性 130
(1) 実行行為の確定
(2) 作為犯との同価値性
5 不真正不作為犯における作為義務 132
(1) 作為義務をめぐる諸説
(2) 保障人説
*保障人的地位と保障人的義務
6 身分犯としての不真正不作為犯 133
2 不真正不作為犯の成立要件...134
1 法律上の作為義務があること 134
(1) 結果発生の現実的危険が生ずること
(2) 結果防止の可能性
*結果防止の可能性と因果関係
(3) 社会生活上の具体的依存関係が存在していること
*緊急救助義務
(ア) 法令
(イ) 契約・事務管理
(ウ) 条理・慣習
(a) 先行行為の場合
*先行行為の事例
(b) 所有者・管理者の場合
(c) 財産上の取引の場合
(d) 慣習の場合
(4) 作為の可能性
*作為の容易性
*作為義務と判例
2 作為義務違反(実行行為) 140
*成立要件と主観的要素
3 不作為による殺人罪と保護責任者遺棄致死罪との区別 141
第3款 間接正犯...142
1 正犯と共犯...142
1 直接正犯と間接正犯 142
2 間接正犯と共犯 142
3 正犯の意義 142
*間接正犯規定の創設
2 間接正犯の要件...143
1 間接正犯の正犯性 143
2 成立要件 144
*規範的障害
3 間接正犯の成立範囲...144
1 身体活動の利用 144
(1) 意思能力を欠如する者の利用
*判例の態度
(2) 行為でない他人の身体活動の利用
*意思を抑圧されている場合
2 一定の構成要件要素を欠く他人の行為の利用 145
(1) 故意のない者の行為の利用
*団藤博士の設例
(2) 適法行為の利用
(3) 身分のない者の行為の利用
(4) 構成要件に該当するが違法性が阻却される他人の行為の利用
3 故意ある幇助的道具の利用 148
*幇助的道具の利用と主観的正犯概念
4 被害者の抵抗できない状態の利用 149
4 自手犯...149
第4款 故意...150
1 故意の概念...150
1 意義 150
2 故意の体系的地位 150
3 故意が過失から区別される根拠 151
2 故意の要件...152
1 犯罪事実の認識 152
*形式的故意概念と実質的故意概念
2 認識の要否および程度が問題になる場合 153
(1) 規範的構成要件要素の場合
*覚せい剤密輸入事件
(2) 因果関係の認識
*実行行為の認識
(3) 違法性阻却事由の認識
*ブーメラン現象
3 意思的要素 157
*故意の本質と判例
3 未必の故意...157
1 意義 157
2 学説 158
(1) 認容説
(2) 蓋然性説
(3) 実現意思説
(4) 動機説
3 判例の立場 159
*未必の故意と過失
4 故意の種類...160
1 確定故意と不確定故意 160
*条件つき故意
2 事前故意と事後故意 161
3 侵害故意と危険故意 161
4 ウェーバーの概括故意 161
5 事実の錯誤と故意の阻却...162
1 錯誤の意義 162
(1) 刑法上の錯誤
(2) 事実の錯誤
2 事実の錯誤の範囲 163
(1) 法律的事実の錯誤
*参考となる判例
(2) 違法性に関する事実の錯誤
(3) 規範的構成要件要素の錯誤
(ア) わいせつ性
(イ) 職務行為の適法性
(ウ) 「たぬき・むじな」事件
(エ) 作為義務の錯誤
3 事実の錯誤の態様 167
(1) 具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤
(2) 客体の錯誤と方法の錯誤
(3) 因果関係の錯誤
4 事実の錯誤の解決基準 168
(1) 学説
(2) 学説の検討
*判例の基本的立場
5 具体的事実の錯誤(同一構成要件内の錯誤) 170
(1) 客体の錯誤
*具体的法定符合説
(2) 方法の錯誤
(ア) 具体的符合説の解決方法
(イ) 法定的符合説の解決方法
(ウ) 諸類型
(a) 併発結果の場合
(b) 過剰結果の場合
*数故意犯説と一故意犯説
(3) 因果関係の錯誤の取扱い
(4) 早すぎた構成要件の実現
(ア) 下級審の判例(横浜地判昭和58年7月20日判時1108号138頁)
(イ) 最高裁の判例(最決平成16年3月22日刑集58巻3号187頁)
(ウ) 取扱い
*遅すぎた構成要件の実現
6 抽象的事実の錯誤(異なる構成要件間の錯誤) 176
(1) 38条2項の趣旨
(2) 解決の基準
(ア) 構成要件の重なり合い
(イ) 重なり合いの意味
*重なり合う場合
(ウ) 諸類型とその取扱い
*38条2項の「処断」の意義
*薬物事犯の判例
第5款 過失...181
1 総説...181
1 過失の意義 181
*刑法上の過失犯
2 伝統的過失論 182
3 新過失論 183
*過失犯の構造
2 過失犯の成立要件...184
1 過失犯の構成要件の特徴―開かれた構成要件 184
2 過失犯の実行行為―客観的注意義務違反 185
(1) 客観的予見可能性
(2) 予見可能性における予見の対象
(ア) 予見可能性の範囲
*危惧感説
(イ) 予見可能性の程度
*中間項の理論
*予見可能性の抽象化
(ウ) 予見可能性と結果回避義務
(エ) 客観的注意義務の基準
*薬害エイズ上告審判決
3 過失行為の主観面―主観的注意義務違反 191
4 信頼の原則 192
(1) 背景
*信頼の原則と判例
(2) 法的性質
(3) 具体的適用
3 過失の種類...195
1 通常の過失と業務上の過失 195
2 重大な過失 196
3 認識なき過失と認識ある過失 196
4 過失の競合...196
1 意義 197
2 単独の行為者の場合 196
3 複数の行為者の場合 197
(1) 監督過失
*監督過失に関する指導的判例
(2) 管理過失
*管理過失と最高裁判例
5 結果的加重犯...199
1 意義 199
*結果的加重犯の態様
2 要件 201
第6款 因果関係...202
1 因果関係の意義と機能...202
1 実行行為と結果 202
*因果関係論と犯罪論の体系
2 因果関係論の機能 203
2 因果関係の理論...203
1 条件説 203
2 原因説 205
3 客観的帰属論 205
(1) 学説
(2) 批判
*【遡】及禁止論
4 相当因果関係説 206
*主観説・客観説・折衷説の解決方法
5 相当因果関係説の妥当性 207
6 折衷説に対する批判 209
3 因果関係の判断方法...210
1 刑法上の因果関係 210
2 条件関係があること 210
(1) 具体的・個別的条件関係
*仮定的因果経過
(2) 択一的競合
(3) 重畳的因果関係
(4) 疫学的因果関係
*疫学
(5) 条件関係(因果関係)の断絶
3 相当性が認められること 214
(1) 相当性の内容
(2) 相当性が問題となる場合
(a) 行為時に不明な特殊の事情があった場合
*特殊事情に関する判例
(b) 第三者の行為が介在した場合
*「第三者の暴行」の介在に関する最高裁判例
(c) 被害者の行為が介在した場合
(d) 行為者の行為が介在した場合
*広義の相当性・狭義の相当性
4 判例の流れ...220
1 四つの最高裁判例 220
(1) 米兵ひき逃げ事件
(2) 熊撃ち事件
(3) 柔道整復師事件
(4) 大阪南港事件
2 危険の現実化説と折衷的相当因果関係説 223
(1) 危険の現実化説の意義
(2) 折衷的相当因果関係説の考え方
5 不作為の因果関係...227
1 不作為と条件関係 227
2 不作為の実行行為と因果関係 227
*不作為の因果関係を認めた判例
第3章 犯罪成立阻却事由...229
第1節 違法性阻却事由...229
第1款 違法性の概念...229
1 違法性の意義...229
1 違法性と違法性阻却事由 229
2 違法性論 230
3 放任行為 230
2 違法性の実質...231
1 形式的違法性と実質的違法性 231
2 法益侵害不可欠の原則 232
3 違法性の客観性 233
(1) 客観的違法性論と主観的違法性論
(2) 新客観的違法性論
(3) 検討
3 違法要素...235
1 客観的違法要素 235
2 主観的違法要素 235
(1) 学説の流れ
(2) 検討
3 人的違法要素 237
4 結果無価値論と行為無価値論 238
(1) 対立の背景
*両者の具体的な対立点
(2) 違法二元論
*わが国の行為無価値論
4 違法性の判断...239
1 判断の基準 239
(1) 「客観的」の意味
(2) 違法性の相対性
2 可罰的違法性の理論 240
(1) 学説
*可罰的違法性の理論に対する諸批判
(2) 検討
3 可罰的違法性と判例 242
4 可罰的違法性の判断方法 243
第2款 違法性阻却...243
1 違法性阻却の意義...243
1 意義と学説 243
2 一般原理 244
2 違法性阻却事由の種類...245
1 正当行為と緊急行為 245
*超法規的違法性阻却事由
2 可罰的違法性阻却事由 245
第3款 正当行為...246
1 総説...246
1 35条の趣旨 246
2 35条の適用範囲 247
2 法令行為...247
1 意義と根拠 247
2 職務行為 248
3 権利・義務行為 248
4 政策的理由に基づく行為 249
5 注意的に規定された行為 249
3 労働争議行為...249
1 意義 249
2 争議行為の正当性 250
(1) 目的の正当性
(2) 手段の相当性
3 公務員・国営企業体等職員の争議行為 250
*二重の絞り論
4 業務行為...252
*「業務行為」不要論
5 その他の正当行為...253
1 意義 253
2 被害者の同意 254
(1) 諸類型
(2) 同意と構成要件該当性
(3) 違法性阻却の根拠
*自傷行為(自損行為)
(4) 被害者の同意の要件
(ア) 処分可能な法益
*国による個人の保護
*同意傷害と判例
(イ) 有効な同意(嘱託・承諾)
*法益関係的錯誤
(ウ) 同意の対象・方法・時期
(a) 対象
*過失犯と同意・危険の引受け
(b) 方法
(c) 時期
(エ) 同意の認識
(5) 被害者の推定的同意
(ア) 根拠
(イ) 要件
(a) 被害者の同意の要件を満たすこと
(b) 被害者の立場から推定すること
(c) 同意を得ることが不可能であること
3 社会的相当行為 258
(1) 治療行為
(ア) 治療行為と傷害
(イ) 不可罰の根拠
*専断的治療行為
(ウ) 要件
(a) 主体
(b) 医学的適応性・医術的正当性
*ブルーボーイ事件
(2) 安楽死・尊厳死・脳死
(ア) 安楽死
(a) 安楽死の諸類型
(b) 安楽死に関する学説
(c) 安楽死の要件
*二つの判決
(α)死期の切迫
(β)耐えがたい身体的苦痛
(γ)明示の嘱託
(δ)補充性
*適用の困難
(イ) 尊厳死
(a) 学説
*尊厳死と判例
(b) 治療中止の許容
(ウ) 脳死と生命維持治療の中止
(a) 学説
(b) 検討
(c) 生命維持治療の中止
*脳死と臓器移植
(3) 自救行為
(ア) 違法性阻却の根拠
*自救行為と判例
(イ) 自救行為の要件
(a) 法益侵害の存在
(b) 緊急性
(c) 被害回復行為の必要性・相当性
(d) 自救の意思
(ウ) 過剰自救行為・誤想自救行為
(4) 業務の衝突
*義務の衝突と判例
(5) 許された危険
第4款 正当防衛...274
1 総説...274
1 意義 274
*緊急行為
2 正当化根拠 275
*判例における正当防衛の趣旨
*戦争と正当防衛
2 正当防衛の成立要件...276
1 急迫不正の侵害 276
(1) 急迫性
(ア) 過去の侵害
(イ) 将来の侵害
*積極的加害意思と急迫性
(2) 不正
(ア) 不正の意義
(イ) 対物防衛
(3) 侵害
2 自己または他人の権利の防衛 280
(1) 自己・他人の権利
(2) 防衛行為
(ア) 防衛行為の結果が第三者に生じた場合
(イ) 侵害者が第三者の物を利用した場合
(ウ) 防衛者が第三者の物を利用する場合
3 防衛行為の相当性(やむを得ずした行為) 282
*具体例
4 正当防衛の意思 284
(1) 学説の対立
*偶然防衛
(2) 防衛意思の内容
(ア) 認識説
(イ) 防衛意思と避難の意思
*過失行為による正当防衛
(3) 判例の立場
5 防衛行為の社会的相当性 288
(1) 自招侵害(自ら招いた正当防衛状況)
(a) 判例・学説
(b) 取扱い
*原因において違法な行為の理論
(2) 喧嘩と正当防衛
3 過剰防衛...291
1 過剰防衛の意義 291
2 質的過剰と量的過剰 292
*量的過剰防衛に関する判例
3 故意の過剰防衛と過失の過剰防衛 293
4 過剰防衛の効果 294
4 誤想防衛...294
1 誤想防衛の意義 294
*誤想防衛と判例
2 誤想過剰防衛 296
*誤想過剰防衛に関する判例
5 盗犯等防止法における特則...297
*盗犯等防止法と誤想防衛
第5款 緊急避難...298
1 総説...298
1 緊急避難の意義 298
(1) 「正対正」の関係
(2) 背景
2 根拠 299
(1) 学説
(2) 学説の検討
*緊急避難に対する正当防衛
2 緊急避難の成立要件...300
1 現在の危難 300
(1) 危難の対象(保全法益)
(2) 現在の危難
*政治亡命
2 避難行為の相当性 302
(1) 補充性(補充の原則)
*つり橋爆破事件
(2) 法益権衡性(法益権衡の原則)
*法益権衡の例
3 避難の意思 303
*過失行為による緊急避難
4 避難行為の社会的相当性 304
*自招危難と判例
5 業務上特別義務者 305
*産婆規則違反事件
3 過剰避難・誤想避難...306
1 過剰避難 306
*過剰避難と判例
2 誤想避難 307
3 誤想過剰避難 307
…………………
以下省略